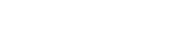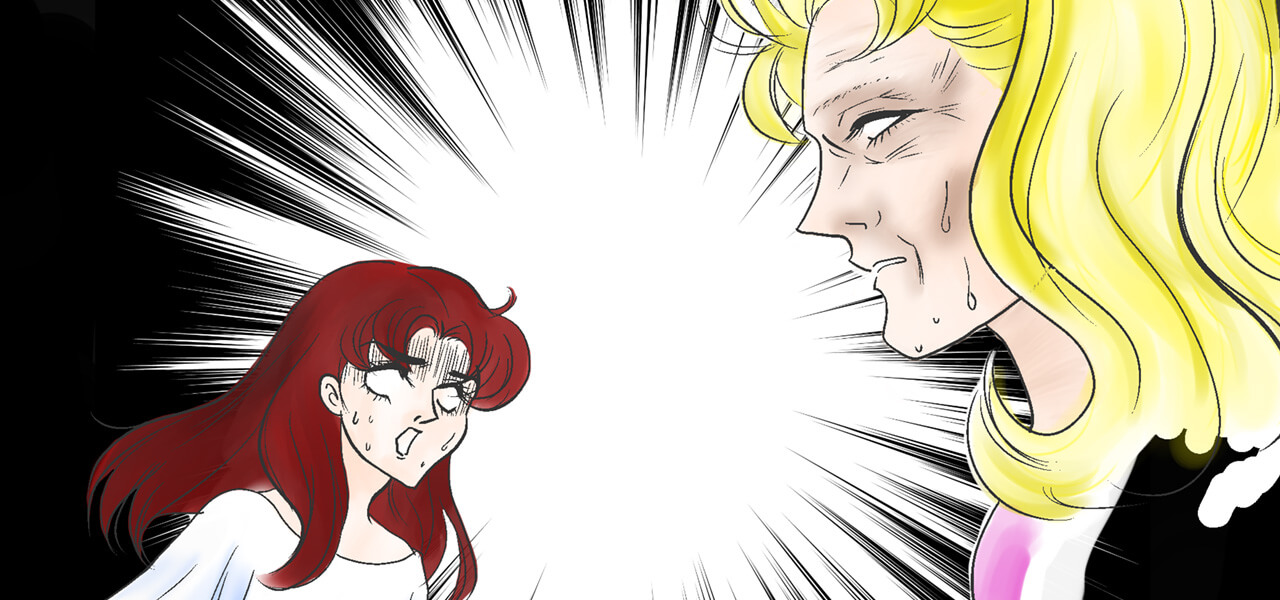「乙女の日本史」シリーズ等で人気の歴史エッセイスト・堀江宏樹の連載がBlack Boardでスタート! ビューティに関するトンデモな歴史や、「美」のために手段を厭わなかった「ビューティ迷子」たちの仰天エピソードをご紹介します。

世界ビューティー迷子録(1)
〜「美」のため“だけ”じゃない、お化粧の歴史〜

「人類が化粧をはじめたのは何時か」という疑問に答える定説はありません。
歴史の中では男女ともに化粧をするのが普通だった時代・文化が、かなり昔からあった……ということは言えるでしょう。
「人間らしくあること」と「美しくありたいと願うこと」は恐らくイコールだからですね。
一方、人間は、自分の素顔に満足できない呪いをかけられた動物だともいえます。だからこそ化粧をしたり、「自分を理想の姿・カタチに調えたい」という欲求に抵抗できないのです。化粧だけでなく、ダイエットや筋トレもそういう文脈で考えればわかりやすいでしょう。
人は化粧をしたくなる……その背景にあるのは、「もっとキレイになりたい!」という悲願だけとも限りません。極論すれば自分の顔を「パワースポットにしてしまいたい!」なんて呪術的な側面も、化粧の歴史にはありました。
たとえば、紀元前3000年ごろのエジプトではすでに、濃いアイラインを描いたメイクの男女がいました。眼ヂカラが凄くて、要するに顔が「魔除け」になっているんですね。
この化粧法は基本的に約3000年もの間、変化することなくエジプト王国の歴史と共に受け継がれたので、流行を超えたシロモノでした。例のアイラインは煤(すす)と脂肪分などを混ぜ合わせたもので描かれています。
ところが、目の粘膜にとって例のアイラインは刺激物なのでした。つまり涙がジワジワと浮かんでくるのですが、それによって、目の粘膜に寄生虫から卵を植えつけられる事態を防止できていたのですね。

……というように歴史の中では、化粧はたんに美しさの追求のためにだけになされていたわけではなかったのがおわかりいただけるでしょう。美以外の実地的な理由もあったはずです。
近世フランスの化粧は「身分」を示すもの
また化粧法は、生まれた身分によって制限すらされがちなものでした。
17世紀後半~18世紀前半のフランスでは、貴族以外、頬紅の使用はNGだったりもしたのです。それゆえ貴族の女たちは頬紅をステイタスシンボルとして塗りたくりました。
当時のヴェルサイユ宮殿は、「おてもやん」みたいな恥ずかしい顔のレディーであふれていたのです。
ちなみにマリー・アントワネットがオーストリアから嫁いでくる18世紀後半にはこの手の化粧をしているのは、老女だけでした。自分が一番よかった時代で化粧の方向性が固定されるのは昔も今もありがちなんですよね。
そして、当時からヴェルサイユの女たちのその手の美(?)は、当事者以外は理解できなかったというのも面白いことです。外国人から見れば「ヴェルサイユのぶす」でしかないのに、当事者にとっては、それが最高にクールだったのですから……。

時代や文化が違えば、おしゃれどころか、ダサくなってしまう……個性的なメイク法になればなるほど、現代でも言えることかもしれません。
「眉なし」メイクは幸せの証
日本の例を見てみましょうか。江戸時代の日本の女性は、結婚したら眉をそり落とすという風習に従っていました。
関西地方では、結婚した時ではなく、最初の子どもが産まれたら眉を剃り落としたり、東北地方ではそもそも眉を剃る風習がなかったりと、地域によるバリエーションはありました。
しかし基本的に既婚女性は結婚指輪をつけるかわりに、眉毛をなくし、自分の幸せを世間様にアピールしたのです。この奥さん方の眉ナシ顔は、外国人たちにはものすごく不評でしたし、現代の日本人にも奇異に思えるため、時代劇の時代考証などでは絶対に守られない美的ルールということになっているのですが。
このように、「お化粧で自分の顔を変えたい!」という欲求は人類の歴史とともにあるのに、何が魅力的なのか、何が美しいのかという問題になると、ほとんど共通する要素が見つからないんですよね。これはすごく不思議なことです。
ということで、今回の連載では日本・世界をとわず、様々な男女の努力の結果をチラチラ覗き見していこうと思います。まぁ、だいたいがマネしてはいけない化粧法・美容法ばっかりなので、よい子の読者は注意してください。
(編注:あくまで読み物としてお楽しみいただけましたら幸いです)